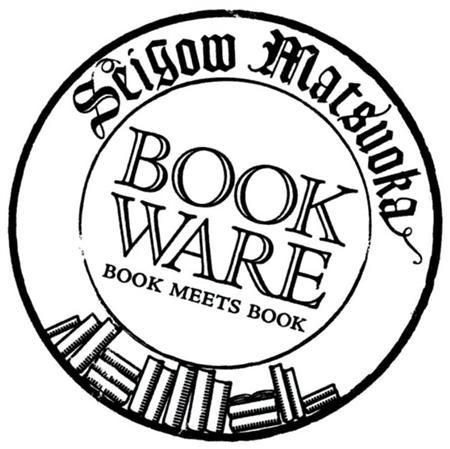〈世界史〉を哲学する社会学者の大冒険 大澤真幸が日本人に「普遍」を引き寄せてくれている 松岡正剛
更新
古代ギリシアではあ「真実を語ること」を「パレーシア」という。世界や社会をどこまでパレーシアできるのか。大澤の壮大な試みは、ヨーロッパが作成した〈世界史〉がイエス・キリストの殺害をどうパレーシアしてきたのかという観察に始まった。難解なテーマを抱えて思索と叙述に挑むのは大澤の「好み」に近い。その「好み」が記述の中で時折とんでもなく重大なキーコンセプトを掴まえる。本書では最後に出てくる「偶有性」が最も重要だ。
ヨーロッパが入念につくりあげた〈世界史〉は、「何を持っているか」というhavingと「何であるのか」というbeingとを、どう重ねられるかという工夫の歴史だった。この中世篇ではキリストの殺害が及ぼす領域すべてに、この「もつ」と「ある」との重合についての試みが検討される。ところが歴史はここに「奪略」(とる)と「利子」(ふえる)という新たな手口を加えた。資本主義はこの新たな手口の正当化に向かって発信していった。